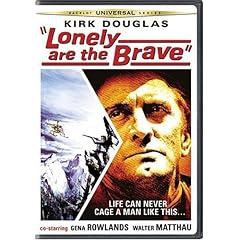365日間映画日誌
日々の映画日記、というか備忘録です。暇な人だけ読んでください。
2009年10月〜12月
2009年12月19日
フィリピン・コネクション〜ヘルマンからブロッカへ
モンテ・ヘルマンのおよそ20年ぶりとなる長編劇映画の新作が、まもなく公開されようとしている(日本公開は未定。というか、まだポスト・プロダクションの段階と思われ、完成しているかどうかも定かでない)。タイトルは、「Road to Nowhere」。泣かせるタイトルだ。『断絶』の続編みたいな題だが、意外にも、映画撮影をめぐる犯罪映画のようである。数号前の「カイエ」に特集が組まれている(見る前によけいな情報を知りたくないので、いっさい読んでいないが)。
☆ ☆ ☆
さて、これからはもう少し、アジア映画について積極的に書いていこうと思う。まずは、わたしの大好きなリノ・ブロッカから。
『Insiang』
リノ・ブロッカ作品でなにか一つ選べといわれたら、『マニラ 光る爪』を選ぶ人が多いだろう。わたしもそうだ。しかし、国際的な知名度という点では、この『Insiang』もなかなかのものである。なにしろこれは、カンヌではじめて上映されたフィリピン映画なのだ(ちなみに、この映画をカンヌにもたらしたのは、またしてもピエール・リシアンだった)。
リノ・ブロッカとフィリピン映画を世に知らしめたこの映画は、彼の作品のなかでは、メロドラマの系列に属するといえるだろう。スラム街のような貧しい一角にすむ母娘。育ててやった恩を忘れたかとばかりに、娘をこき使う抑圧的な母親は、やがて息子ほども年の離れた愛人を家に引き入れる。だが、男の目当ては娘のほうだった。母親の愛人に乱暴され、絶望した娘は、この環境から恋人とともに逃げだそうとするが、恋人にも裏切られ、失意のうちに帰宅する。娘は愛人に、自分を裏切った恋人をリンチさせ、その愛人を母親の嫉妬心を利用して殺させる。ラストの母と娘の断絶のシーンが、唯一の救いに見えてくるほど、物語には救いがない。
修道院で暮らしていた汚れを知らない少女が、何者かにレイプされ、犯人の子供を妊娠する。少女は、子供を手放すことを拒んで、修道院から逃げ出す。転落の人生を歩む彼女がやっとつかんだ幸せな結婚相手は、実はレイプ犯だった。『O公爵夫人』を思わせる展開だが、むろん、あんな風に丸く収まるわけがない。
宗教的背景、貧しい社会環境、残酷な展開。メキシコ時代のブニュエルと比較したくなるような作品である。最後におきる嘘のような奇跡もブニュエルっぽいが、ブニュエル作品ならついニヤリとしてしまう、そんな取ってつけたたような結末が泣かせるのは、一見何もかも安っぽいこの映画が、実は、とても丁寧に描かれているからだ。
どちらの主人公も、他のブロッカ作品同様、映画が始まったときと終わったときでは、まるで別人に変化している(修道院で始まり修道院で終わる『神への祈り』のほうが、その変わり様はより鮮やかに映し出されているといっていい)。『目覚めよマルハ』ではないが、リノ・ブロッカの映画はどれも、一言でいうなら、「意識の目覚め」の物語なのだ。この目覚めの物語を、メロドラマとアクションと矛盾なく融合させたところが、ブロッカ作品の醍醐味である。『Insiang』の一見救いのない物語も、眠っていたヒロインが最後に目覚めるという点では、どこまでもポジティヴなのだ。
リノ・ブロッカは、実は、映画監督になる前に、モンテ・ヘルマンのもとで働いた経験を持つ(なんたる偶然!)。『Flight to Fury』や『Back Door to Hell』といった、フィリピンで撮られたヘルマンの第二次大戦ものの撮影に、スクリプト・アドヴァイザーとして参加していたのだ。 四方田犬彦の『アジア映画の大衆的想像力』によると、フィリピンを半世紀近く植民地支配していたアメリカは、「アジアのハリウッドをマニラに建設しようという、はっきりとした意図をもって植民地経営を行った」という。そういうわけで、フィリピン映画はこの頃には非常に隆盛を極めていたと思われる。まだ映画を撮りはじめる前のリノ・ブロッカが、モンテ・ヘルマン組に参加したのは、そんなころだった。ブロッカは、モンテ・ヘルマンの撮影現場で、映画作りのノウハウを学んだのである。(ブロッカが登場したときの、フィリピン映画とアジア映画の状況は、四方田犬彦の同書を参照。もっとも、四方田はモンテ・ヘルマンのことにはまったくふれていない。)
だから、ブロッカの低予算早撮りはモンテ・ヘルマン譲りのものだったのだ──、と話をまとめたいところだが、実情は違っていたようだ。ミシェル・シマンの『Petite planète cinématographique』のインタビューによると、何度もテイクを取り直したり、些細なことでもめて撮影をストップするモンテ・ヘルマンの撮影ぶりを、ブロッカは「遅すぎる」と感じたらしい。ロジャー・コーマン仕込みのモンテ・ヘルマンの映画作りさえ、やがてフィリピンを代表する監督となるこの青年には、贅沢なものと思えたのだ。このことだけでも、ブロッカの映画は、ハリウッド流の映画に対する批評となり得ている。
2009年12月8日
キューバ・リブレ〜『ある官僚の死』『12の椅子』
トマス・グティエレス・アレア『ある官僚の死』(66)
この作品については、一度紹介しようと思ったことがあったのだが、さして興味を引きそうにもなかったので、書く前にボツにしてしまっていた。日本ではほとんど見る機会がないし、海外の DVD をわざわざ注文してまで見ようと思う人間もいないだろう。書いても無駄だ。
──と思っていたら、「キューバ映画祭2009」というのが開催され、ここでこの作品が上映されることがわかった。すでに東京での上映は終わっているが、12月12日から京都シネマでも開催されるようなので、関西の人にはこれから見ることが出来る。というわけで、簡単に紹介しておく。
グティエレス・アレアは、言うまでもなく、キューバを代表する映画作家で、今回上映される作品12本のうち、実に4本が彼の長編である(短編もふくめれば、プログラムのほぼ半分が彼の作品だ)。
正直言うと、この人がそんなにすごい監督だとは思っていない。ただ、『苺とチョコレート』『低開発の記憶』といったシリアスな作品ばかりが公開されて、彼のコメディが全然紹介されていないというのは、どうにもバランスが悪い。本人がどう思っているかはともかく、わたしが思うに、この監督の本領はコメディにあるように思えるのだ。『ある官僚の死』はそんな彼のコメディの代表作である。
社会主義のキューバでひとりの模範的な労働者が亡くなり、埋葬された。未亡人が役所に年金を受け取りに行くと、それには死んだ夫の組合員証が必要だということがわかる。ところが、その組合員証は棺といっしょに埋葬してしまったので、手元にない。だったら遺体を掘り起こして、組合員証を取り戻せばいいだけのことだ。そのはずだった……。未亡人の甥が組合員証を取り戻そうとするが、遺体を掘り起こす許可は簡単には下りない。しかたなく甥は、真夜中、墓地に行って、無断で死体を掘り起こす。だが、その最中に、警官に見つかってしまい、慌てて死体を家に持って帰る。今度は、掘り起こした死体を元に戻さなければならない。ところが、またしても役所の許可が下りない。すでに埋葬してある死体を、また埋葬することなど出来ないというのだ……。
硬直したシステムから生まれる滑稽な状況を描いたこの映画は、ときに安直に「カフカ的」などと評されもする。だが、この作品は、官僚制というものを、『未来世紀ブラジル』のように、日常の向こうにある異様な世界、あるいは日常の底に潜む不条理として描くのではなく、キューバの社会主義の日常そのものとして風刺している。 一つの死体を巡る騒動という意味では、『ハリーの災難』に似ていなくもないが、ブラック・コメディというよりは、スラップ・スティック色のほうがはるかに強い作品だ。墓場の場面は、ローレル・ハーディの短編を思わせるし、主人公が役所の時計台にしがみつくロイドばりのシーンさえある。ここにハリウッド喜劇の影響を見て取るのはたやすい。もっとも、ここにはたんなるオマージュというよりは、資本主義国アメリカ製のコメディに対するパロディ的な意味も多分に込められているのだろう。
「キューバ映画祭2009」で上映されるグティエレス・アレアのもう一本、『12の椅子』(62)も彼のコメディの代表作の一つだが、『ある官僚の死』とくらべると、オリジナリティに欠けるし、あまり成功しているともいえない。しかし、社会主義に移行して間もないキューバ社会のありようは、『ある官僚の死』以上にこの作品にくっきりと表れているともいえる。
キューバが社会主義政権に変わったために、財産を政府に没収されてしまったひとりのブルジョワ男が、この映画の主人公だ。彼の叔母は、死ぬ直前、高価なダイヤモンドを、自宅の12個ある椅子の一つに隠していた。しかし、その椅子はすべて政府に没収され、国中にばらばらに引き取られてしまっている。しかも、まったく同じかたちをした12の椅子の、どれにそのダイアが隠されているかわからない。男は、椅子の行方を追って、しらみつぶしに探してゆくが、見つかった椅子はどれもハズレ。その上、ダイアのことを知っているライヴァルが、同じように椅子を探していることがわかり、ますます焦り始める……。
この映画を見ていて思い浮かべたのは、ハリウッド喜劇ではなく、イーリング・コメディ『ラベンダー・ヒル・モブ』だ。盗んだ金塊をエッフェル塔のミニチュアに変えたまではいいものの、手違いでそれがどこに行ったかわからなくなるという後半のくだりが、似ていなくもないのだ。もちろん、影響関係云々をいっているのではない。ただ、グティエレス・アレアが影響を受けたのは、よく指摘されるネオ・リアリズム(彼は、戦後間もないころ、ローマに留学して、ネオ・リアリズムの洗礼を受けている)だけでないのはたしかだろう。
このお話自体は、当時としてもそれほど目新しいものではなかったかもしれないが、この映画の真の見所は、主人公が椅子の行方を追うのと同時に、キューバの社会主義の様々な現実をキャメラが切り取っていくところにある。グティエレス・アレアは、この映画の撮影中、ロケハンで見つけた場所が、次に行ったときには、ブルジョワの邸宅がアート・スクールにといったぐあいに、以前の面影がないぐらい変わってしまっていたという体験を何度もしたという。ここに描かれているのは、急激な勢いで変わりつつあるキューバの姿だ。そういう観点で見るなら、なかなかに興味深い作品である。
グティエレス・アレアは、革命前のキューバで、ネストール・アルメンドロスと何度も活動をともにしている。アルメンドロスはその後、社会主義化したキューバを離れ、キューバを外側から批判的に描くドキュメンタリーを製作するが、グティエレス・アレアは、社会主義に移行したキューバで数々のプロパガンダ映画を撮り、やがてキューバを代表する監督になってゆく。彼の長編劇映画は、決して、現状を盲目的に肯定するものではなく、キューバの社会を批判的に描く視点も持ちあわせており、『低開発の記憶』のようにニュアンスに富んでいたりする。しかし、アルメンドロスが撮ったドキュメンタリーと比較すると、やはりどうしても踏み込みが甘く見えてしまうのもたしかだ。
「キューバ映画祭2009」には、アルメンドロスの作品が入っていないのは残念である。彼もキューバにおけるゲイの抑圧された状況を描いていたはずなので、グティエレス・アレアの作品と比較してみれば興味深かったろう。このブログで紹介した『怒りのキューバ』が入っていないのも、もったいない(『怒りのキューバ』は、今年になって3枚組の DVD コレクターズ・エディションがでている。スコセッシがいつものように熱っぽい早口で、この映画のことを語っている特典映像もはいっている)。いずれも厳密に言うなら、キューバ映画にはならないのかもしれない。しかし、事情が許すなら、これらの周辺作品もぜひ入れてほしかった。(アルメンドロスとキューバの関係については、『キャメラを持った男』を参照。)
下写真は、アルメンドロスがキューバを描いたドキュメンタリー『Nobody Listened』。
2009年12月2日
シドニー・ギリアット『青の恐怖』
シドニー・ギリアット『青の恐怖』Green for Danger
ヒッチコックの『バルカン超特急』などの脚本家としてのほうが有名なイギリスの映画監督、シドニー・ギリアットによるミステリー映画。
『絶壁の彼方に』という映画が結構気に入っていたのだが、他の作品は見たことがなかった。この作品を見て、やはりなかなかの才能だと確信した。(『絶壁の彼方に』については、『たかが映画じゃないか』で山田宏一と和田誠が楽しげに話題にしている。ビデオがレンタルで借りられるはずだが、置いている店はほとんどないので見つけるのは難しいだろう。)
第二次大戦末期のイギリスの片田舎にある病院が、『青の恐怖』の舞台だ。冒頭、この映画の主要人物となる医者やナースが勢揃いしてオペをおこなっている場面にかぶさってナレーションが、ひとりひとりの人物紹介をおこなってゆき、最後に、「この中のふたりが死ぬ。そしてこの中のひとりは犯人だ」と結ぶ。 実際、彼らが手術したひとりの患者が麻酔処理中に急死する。手術のプロセスには何のミスもなく、事故死と判断されるが、「あれは殺人よ。証拠のありかも知っている」と口走ったナースが、直後に殺され、連続殺人の可能性も浮かび上がる……。
なんだか、「チーム何とかの栄光」を思わせるような話ではないか。このあとスコットランド・ヤードの警部が事件の捜査に乗り出してくるのだが、関係者全員を平等に疑い、ずけずけと質問するこのサディスティックな警部も、あの日本の医療ドラマに出てくる調査員に、似ているといえば似ている(アラステア・シムが、切れ者でかつコミカルな警部をエキセントリックに演じている)。これが元ネタといわれても、別にわたしは驚かないだろう(もちろん、何の根拠もない推測だが)。
巧みなプロット、大胆なトリックで、日本のミステリー・ファンにも評価の高いクリスチアナ・ブランドが原作(『緑は危険』)なだけに、ミスリーディングを誘う手がかりがあちこちにもうけられ、勘のいいわたしにも結末は予測できなかった。しかし、謎解きにはさして興味のないわたしには、実はそのあたりは別にどうでもいいというか、とりあえず有無をいわせず話が前に進んで行きさえすればいいのだ(『三つ数えろ』のストーリーは何度見てもわからないし、映画なんてそれでいいのだ)。
この作品に惹かれたのは、複雑なプロットや、巧みなストーリー展開にではない。この映画の魅力は、なによりもその一種異様なダークな雰囲気にある。見終わったあとで夜の場面しかなかった気がするぐらい、終始、薄暗い照明で撮られたモノクロ画面を見ていると、ギリアットがドイツ表現主義映画やラングの『M』を夢中になって見たという話もうなずける。オープンセットで作られた、病院前の庭園のおどろおどろしい雰囲気もいい。 戦時中という設定は、物語にほとんど直接的には関わってこないのだが、この映画に特異な雰囲気をもたらすことに大いに役立っている。
夜空をときおり爆音を響かせて飛んでゆくナチのV1ロケットが、とりわけ印象的だ。V1ロケットが飛んでいくのがこんなにはっきりと見える映画は初めての気がする。どれほど正確に再現されているのかはわからないが、奇妙な形をしていて、想像していたよりもずっとゆっくりと空を滑ってゆく。この遅さがよけい不気味だ。姿が見えるのは最初の一度だけだったと思うが、間欠的に聞こえるロケットの爆音は、いつそれが近くに落ちてくるかわからないという恐怖よりも、目に見えない漠然とした不安となって、作品に独特の緊張感をもたらしている。
Criterion Collection の DVD で見たのだが、今月の上旬にジュネス企画から DVD が出ることを、書いている途中に知った。細かいサインを読み解きながら、サスペンスを楽しむには、当然、日本語字幕で見るのがいいのに決まっているが、Criterion の DVD の画質は非常にすばらしく、つやつやと輝くようなモノクロ画面は見ていて気持ちがよかった。ジュネスの DVD の状態がこれほどいいとはとても思えない(むろん、見ていないので、たんなる推測だ)。
忘れてしまうにはあまりにも惜しい作品である。とにもかくにも、これをきっかけに、この監督がもう少し注目されるようになることを期待する。
蛇足だが、"Green for Danger" が「青の恐怖」となっているのは、別に誤訳という訳ではない。 「green は yellow と blue の間の色で, 時に blue も含む. 一方, 日本語の「青」は広義には「緑」も含むので, green =「青い」となることが多い: 〜 fields 青々した野原/The light went 〜. 信号が青になった.」(『ジーニアス英和大辞典』)
もっとも、この映画は白黒なので、緑も青も関係ない。「青」にしたのは、その方がかっこいいからという理由だったかもしれない。
あと、Criterion の DVD に収録されていコメンタリーのなかでは、Gilliat は「ジリアット」と発音されているようだ。「シドニー・ジリアット」と表記するほうが、原音に近いのかもしれない。
下は Criterion 版。
2009年11月26日
芝居をせんとや生れけむ〜『二重生活』『Shakespeare-Wallah』
■ジョージ・キューカー『二重生活』A Double Life
40年代末から50年代末にかけてキューカーは、ガーソン・カニンとルース・ゴードン夫妻の脚本をもとに、『アダム氏とマダム』、『ボーン・イエスタディ』、『有名になる方法教えます』をはじめとする傑作7本を、立て続けに撮っている。キューカーがカニン夫妻と組んだ作品はほとんどがコメディだが、最初の作品『二重生活』だけはとてもシリアスで、ノワールな作品だ。
フランスでの公開タイトル「Othello」が物語るように、この映画はシェイクスピアの『オセロ』のかなり自由な翻案と考えることも出来る。
ロナルド・コールマン演じる有名な舞台俳優が、この映画の主役だ。冒頭、彼に挨拶された男が、「あいつはいいやつだ」というと、その場にいた別の男が、「ひどいやつさ」と応じる。その直後、コールマンに声をかけられた女が、「すてきな人ね」というと、一緒にいた女性がすかさず、「最低の男よ」と答える。こんなふうに、観客におやっと思わせるやりとりで映画は始まる。 名優ではあるが、この俳優にはひとつ問題があって、それは演技にあまりにものめり込みすぎて、芝居の公演がつづいているあいだずっと、自分が演じているキャラクターを引きずってしまうことだ。だから、コメディを演じているときは、陽気な人間なのだが、いやな人物を演じているときは、最低の人物にもなる。前の妻と離婚する羽目になったのは、そんな性格が災いしたためだ。
彼が最初、『オセロ』役を断るのは、なにか悪い予感がしたためかもしれない。しかし、結局は出演することになり、彼の『オセロ』は大ヒットする。デスデモーナの役を演じるのは、彼の元妻だ。彼の人格はやがてオセロに乗っ取られ、フィクションと現実の区別が次第に出来なくなってゆく。ついには元妻の不実を疑いはじめ、やがて殺人事件まで引き起こすことになる……。 フィクションと現実の二重生活。舞台上の『オセロ』と、主人公の妄想のなかで『オセロ』と重なってゆく現実の二重構造。アイダ・ルピノの『二重結婚者』では、二重生活を生きる哀しい男を演じていたエドモンド・オブライエンが、ここでは逆に、二重生活を告発する役回りを演じているところが面白い。
この作品は、しばしばフィルム・ノワールの一本に数えられる。映画のなかで殺人が起きるのは、物語のやっと後半になってからだが、ミルトン・クラスナーによるロー・キーで撮られたコントラストの強い画面は、終始作品に不安な雰囲気を与えており、この映画をキューカーとしては例外的なぐらい陰鬱なものたらしめている。しかし一方で、「鏡を撮った男」(武田潔)クラスナーが執拗に映し出してみせる反射のイメージは、『男装』や『スタア誕生』といった多くのキューカー作品に描かれる「演技」と「実像」という主題と響きあい、この作品を実にキューカー的なものにしているといっていい。 キューカーがこのような作品を撮れたのは、製作したのがそれまでの古巣MGMではなく、ユニヴァーサルだったことが大きな要因だったはずだ。絢爛豪華なMGMでは、『二重生活』のような実験的作品は作らせてもらえなかったろう。実際、この作品の成功が、MGMに『アスファルト・ジャングル』を作らせる決断をさせたのにもかかわらず、MGMの首脳陣は、完成した『アスファルト・ジャングル』にあまり好印象を持たなかったという。 また、この作品に描かれるニューヨークの描写を、『裸の町』のニューヨーク・ロケに先立つものと見ることも出来る。こういうふうに見てくると、映画史的にもこの作品は密かに重要な役割を果たしているといっていいだろう。
「鏡像」「分身」「アイデンティティの喪失」といった現代的なテーマが扱われている作品だが、そこはジョージ・キューカーだ、観客を真の意味で不安に陥れることは決してない、古典的な風貌に収まっている。
[関係ないが、思い出したのでついでに書いておく。最近、ロバート・シオドマクの『暗い鏡』を久しぶりに見直した。オリヴィア・デ・ハヴィランドが一卵性双生児の姉妹を演じる犯罪スリラーだ。どちらが姉でどちらが妹なのか時に区別がつかなくなる、めくるめく映画というふうに覚えていたのだが、見直してみて、二人を演じるハヴィランドの服には、必ず名前が書いてあることに気づいた。映画のなかでは、彼女が勤める店の店員をふくめ、だれも彼女たちが双子だと気づいていなかったという設定になっているのだから、服に名前が書かれているのは、観客に区別しやすくするためとしか思えない。なんて親切なんだ! しかし、最後に生き残る正常な方のハヴィランドの利き腕が逆になっていたような……。まさか、『スキャナーズ』じゃあるまいし、わたしの勘違いだろう。(ちなみに、この作品もミルトン・クラスナーがキャメラを担当している。無論、どこもかしこも鏡だらけの映画だ。)]
■ジェームズ・アイヴォリー『インドのシェイクスピア』(SHAKESPEARE-WALLAH, 65, 未)
『二重生活』について予定以上に長く書いてしまったので、こちらは簡単に紹介しておく。 ジェームズ・アイヴォリーという監督にはほとんど興味を持っていないのだが、あるところでゴダールが、「とても素晴らしい作品」と書いているのを読んで以来、この作品だけはずっと見たいと思っていたのだ。結論からいうなら、その後のアイヴォリー作品と大差のない作品だった。しかし、描かれているテーマが興味深かったし、低予算で撮られているためか、文芸映画っぽくないところも悪くない。
アイヴォリーが一時期、インドで暮らしていたことは意外と知られていないようだ。インドについてのドキュメンタリーを依頼されたのをきっかけに、彼はインドに数年間滞在することになり、そこでインドを舞台にした映画を何本か撮っている。『インドのシェイクスピア』もその一本だ。アイヴォリーを国際的に有名にしたのは、この作品だった。(ちなみに、インドで撮られたドキュメンタリー作品『The Delhi Way』も、『SHAKESPEARE-WALLAH』の DVD のなかに収められている。)
この映画が描くのは、英国による植民地主義の薄れゆくインドで、シェイクスピアを演じて旅回りをしている英国人一家の一座だ。この頃には、演劇はかつてのような娯楽の中心ではなく、映画に取って代わられようとしている。今まで芝居をさせてもらっていた小屋に、次回からの公演を断られるなど、一座の先行きも明るくない。そんなとき、看板女優の娘が、旅先でインドの金持ちのプレイボーイに恋をするのだが、彼にはすでに愛人がいて、それが皮肉なことに、有名な映画女優なのだ。 プレイボーイのお遊びには慣れっこの映画女優が、それでも我慢できなくて、彼の新しい恋人が出演している舞台を見に行く場面がある。自分が2階桟敷に現れれば、観客はお芝居などそっちのけで、自分に注目が集まることがわかっていての、嫌がらせだ。恋の三角関係に、演劇という伝統文化の衰退と、映画の台頭が重ねられているところがわかりやすい。おそらく、シェイクスピアなど一度も読んだことがないに違いない無知な映画女優の姿に、映画という芸術がもともと持っているある種の野蛮さのようなものが体現されているようにも思える(もちろん、制作者にその意図はなかったろうが)。
2009年11月22日
小島信夫『美濃』、スコリモフスキ『早春』のことなど
『アンナと過ごした4日間』を見に行ったついでに、京都駅前のビルにあるアバンティ書店にデ・フォレの『おしゃべり、子供部屋』を買いに行く。このあたりではいちばん大きな本屋なのだが、置いていない。まあ、こんなものか。さすがに平積みはしてないだろうと思ったが、ちょっとがっかり。そのかわり、小島信夫の『美濃』が文庫になってるのを見つける。見ると、今月出たばかりのようだ。講談社文芸文庫、1700円。相変わらず高い。600円を超えたら、それはもはや文庫ではない、とわたしは思う。が、ここでしか買えないのだから仕方ない。迷わず購入。 帰りの電車の中でさっそく読みはじめる。語り手の作家の評伝を、彼の郷里の知人作家が書く。のっけから「彼」と「私」という人称が、まるで交換可能なものであるかのように、曖昧に揺らいでいる。この小説、最初からなんだかきな臭いぜ。
ところで、イエジー・スコリモフスキの『アンナと過ごした4日間』は、すごい傑作だった。マスコミで報道されたら「ストーカー」ということで簡単に片付けられてしまうに違いない、そんな中年男の起こした事件の内実が描かれるのだが、ひょっとしたら『早春』の若者が中年になったらこんなだったかもしれない、と、そんなことを考えながら見てしまった。『早春』(もちろん、小津じゃなくて、スコリモフスキのほうです)をテレビでたまたま見たのは、まだ大学に入る前のころだったはずだ。しかし、その一度見ただけの印象は強烈で、今でも幻のように覚えている。主人公の青年が、レストランのウエイトレス(だったと思うのだが)に恋をし、店の前に飾ってあった彼女の等身大パネルを盗み出す。そして、プールの飛び込み台の上からそのパネルを投げ込み、水に浮かんだそのパネルに向かってダイブするのだが、その瞬間、あるはずのない彼女の髪の毛が水中にふわっと広がるのだ。忘れがたいシーンだ。 (そういえば、ジェレミー・アイアンズさえ、『Moonlighting』では、ポーランドを遠く離れた異国のアメリカで、服飾店の店員を口説こうとして、あっさり振られていた。スコリモフスキーの映画にはあまりモテる男は出てこない。)
☆ ☆ ☆
いずれ、紀伊国屋から『アンナと過ごした4日間』の DVD が出ると思うが、そのときぜひ、この『早春』と、あと『フェルディドルケ』もついでにソフト化してほしい(劇場で公開されるのがベストだが、そこまでは期待しないので)。
2009年10月26日
No Country for Old Men〜デイヴィッド・ミラー『脱獄』
デイヴィッド・ミラー『脱獄』Lonely are the Brave (62)
デイヴィッド・ミラーという監督は、日本では『ダラスの熱い日』が多少とも知られているだけで、さして評価が高いわけではない。アメリカ本国でも、オリジナリティーに欠ける凡庸な監督というのが、一般の評価である。そして、多分、この評価は間違ってはいない。実際、この監督には、作家として称揚すべき個性も野心も欠けているのだ。しかし、わたしは彼が撮ったこの『脱獄』という映画が大好きなのである。 出来がいいか悪いかといえば、取り立てて出来のいい作品ではない。しかし何とも忘れがたい作品だ。
冒頭、見渡す限りの荒野をカウボーイ姿のカーク・ダグラスが馬に乗って登場する。だれが見ても西部劇だ。しかし、彼が馬で大きな河を渡ると、その先には、アスファルトの道路を車が激しく往来している。まるでヴェンダースの映画のような始まり方だ。 カウボーイ男は、クラクションを浴びせかけられるのもものともせず、馬に乗ったまま道路を横断する。近くの一軒家で、女がひとり家事をしている。ジーナ・ローランズだ。表から聞こえてくる蹄の音になにかを察して、女は笑みを浮かべる。ほどなくして戸口に現れるのは、無論、カーク・ダグラスだ。こんなふうに、この映画は帰郷の場面で始まるのだが、ここは、『ラスティ・メン』の冒頭で、ロデオ乗りのロバート・ミッチャムがふらりと帰ってくる少年時代の思い出の家のような親密な場所ではないし、女も彼の家族ではない。実際、この男には帰るべき場所などどこにもないのだ。それがこの映画のテーマでもある。
ジーナ・ローランズとカーク・ダグラスの交わす会話から、女はダグラスがかつて愛した女性で、今は彼の親友と結婚して子供もいること、そしてその親友は町の牢屋に入れられていることがわかる。いまだにあてどない生活をしているのかと女に聞かれたダグラスは、こう答える。「おれはフェンスが嫌いなんだ」。このセリフを聞いてはたと気づく。この映画はキング・ヴィダーの西部劇『星のない男』の続編なのだ。あの映画を見たものなら、土地を囲い込む有刺鉄線を異常なほど憎む主人公のカウボーイのことを忘れることはできないだろう。その主人公を演じていたのも、カーク・ダグラスだった。
『脱獄』の脚本を書いたダルトン・トランボがこのことをどれほど意識していたかはわからない。しかし、この映画を自らプロデュースしているカーク・ダグラスは、間違いなくこの2つの作品の血縁関係を意識していたと思う。『星のない男』の続編といったが、むろん、本当の続編ではない。『星のない男』とその7年後に撮られた『脱獄』では、主人公の名前は違うし、物語の時代設定は10年どころか、100年近い隔たりがある。『星のない男』で、自分の行動を制限するフェンスを嫌悪し、それが原因でときに理解しがたい暴力の発作に襲われもした主人公のカウボーイは、『脱獄』でも相変わらず、牢屋の鉄格子はもちろん、フェンスや国境といった境界線に対して嫌悪感を示す。しかし、『脱獄』のダグラスは、ひとつの場所に安住できない自分の性癖がすでに時代遅れなものだとわかっており、なかば仕方なくその性癖に従っているようにも見える。 親友であるジーナ・ローランズの夫が牢屋に入れられていることを知ったカーク・ダグラスは、牢屋に入れてもらうため、酒場でわざと騒ぎを起こす(この酒場の場面では、客の一人の戦争で片手を亡くしたという男が、陰険に描かれているところが面白い)。『星のない男』では内側の暴力を抑えきれない男を演じていたダグラスだが、『脱獄』ではもっぱらいわれなき暴力を受けるだけの存在になっている。牢屋でサディスティックな保安官ジョージ・ケネディにリンチされるシーンがその典型だ。
『星のない男』の主人公を現代社会にさまよわせるという主題は、野心的であり、美しい。しかし、監督の手腕がそれに見合っているかという問題はたしかに残る。似たような冒頭を持つフォードの『捜索者』が、ほとんど視線のやりとりだけで人間関係をすぐにわからせてしまうのにくらべ、『脱獄』のローランズ、ダグラス、マイク・ケインの関係の描き方は、もたもたしているわりに舌足らずだ。牢屋の場面もお世辞にもうまいとはいえない。たぶんこの監督は人間関係を描くのが苦手なのだ。後半の山越えのシーンが感動的なのは、ここではカーク・ダグラスのほとんど一人舞台になるからだろう。このクライマックスで、ダグラスは小高い岩山を馬に乗ったまま乗り越えようとする。途中で馬を捨てれば楽にいけるものを、愛馬を捨てることができず、越境は次第に困難なものとなってゆく。この主題がまた、船で山を登るヴィダーの西部劇『北西への道』に似てしまっているのは、はたして偶然なのか。 巨大な山にひとりで挑み、ヘリコプターをライフルで撃ち落とそうとするダグラスはまるで、愛馬ロシナンテに跨ったドン・キホーテのようだ。『星のない男』が『ドン・キホーテ』前編だとしたら、この後編では、西部劇はすでに物語のなかにしか存在しない世界になっており、主人公もなかば自意識に目覚めている。その主人公を追いつめる保安官たちが、ジョージ・ケネディ、ウォルター・マッソーといった、主に60年代以後に活躍し始める新世代の俳優たちであるというのも、実に象徴的だ。 ネットでざっと調べてみて、日本でもこの映画が好きな人間が意外と多いことがわかった。しかし、この作品と『星のない男』との血縁関係をだれも指摘していないようなのには驚く。見ていればだれもが気づくはずだ。それに気づかないということは、『星のない男』さえ、だれもまともに見ていないということなのか。 最後にやってくるあっけない結末は、アメリカン・ニューシネマを思わせるというコメントも散見された。たしかに、『バニシング・ポイント』に代表されるような、無軌道な暴走の果ての自死に、それは似ていなくもない。しかし、この映画を映画史のなかに正当に位置づけたいのなら、『星のない男』を見てからにしてほしい、とだけいっておく。
2009年10月9日
アンジェイ・ムンク『やぶにらみの幸福』
たまたまアンジェイ・ムンクの映画を何本か DVD で見、ついでに、ちょっと前に衛星放送で録画したまま放っておいたワイダの『世代』をようやく鑑賞し、1年以上前に買っておいたスコリモフスキーの『Moontlighting』の DVD をやっと開封し、ポーランド映画のことを少し調べていたところだったので、ロマン・ポランスキーがスイスで逮捕されたというニュースを聞いたときは、とても驚いた。むかし起こした例の少女暴行事件が逮捕理由だそうだから、三浦なにがしの事件を思い出させる展開である。Le Monde のウェッブ版にはこの事件についての記事がすでに山のように書かれていて、ポランスキーはひょっとしたら、わたしが知らないうちにフランスに帰化していたのかと思ったぐらいだ(そうなのか?)。文化相のフレデリック・ミッテランが逮捕に疑義を唱えると、それを緑の党のダニエル・コーン=ベンディットがたしなめるといった具合に、この事件はフランス政界にも波紋を及ぼしている(そういえば、CRITERION から出ている『ポケットの中の握り拳』の DVD だったろうか、特典映像のなかの字幕で、コーン=ベンディットの綴りが間違っていたのを思い出した)。 アメリカでも、ウディ・アレンやスコセッシらが釈放を求めてすでに署名活動に動いているとも聞く。日本ではあいかわらず、日本人とハリウッド俳優が関わっていないニュースには関心が薄いようだ。ウェッブ以外では、大して話題になっていないように思える。
☆ ☆ ☆
アンジェイ・ムンク『やぶにらみの幸福』(Zezowate szczescie, 60)
ワイダやカワレロヴィッチ、あるいはポランスキーといった戦後ポーランド派の作家たちや、キェシロフスキなどの作品が数多く公開される一方で、いまだに日本では冷遇されつづけているポーランドの映画作家たちがいる。ポーランド映画のヌーヴェル・ヴァーグの筆頭クシシュトフ・ザヌーシ、イエジー・スコリモフスキー、そしてワイダやカワレロヴィッチとほぼ同世代のアンジェイ・ムンクもその一人だ。 日本では、ムンクの映画は、フィルムではもちろん、ビデオでもほとんど見ることができない。わずかに『パサジェルカ』がビデオになっているぐらいだ。これも、今となっては探し回らなければ見つからないだろう。DVD が出る気配もまったくない。幸い、海外では、ムンクの長編映画は、今ではほとんど DVD で見ることができる(もっとも、ムンクはその生涯でわずか数本の長編しか撮っておらず、しかもそのうちの一本は未完のままだ。全部まとめても、BOX 1個に余裕で収まってしまう)。
『やぶにらみの幸福』はムンクが遺作『パサジェルカ』の前に撮った最後から2番目の長編映画だ(「やぶにらみの幸福」というのが、この映画の原題の直訳なのかどうか、わたしには分からない。邦訳の出ているマレク・ハルトフの『ポーランド映画史』のなかでそう訳されていたので、とりあえずそのまま使ったが、いささか意味不明の表現だ)。この映画を見ると、ムンクが『パサジェルカ』一本で片付けられるような作家ではないことがよくわかる。彼の数少ない作品のなかでも、おそらく最も重要な一本といってもいいだろう。だが、この作品の話をする前に、『エロイカ』という映画について少しふれておきたい。
『エロイカ』は、『やぶにらみの幸福』の1つ前の長編映画で、ムンクが撮った最も有名な作品といってもいいだろう。この映画は、第二次世界大戦を描いた2つのエピソードより構成されていて、2つの挿話はともにポーランド人のロマン的英雄主義とでもいったものを主題にしている(『エロイカ』はもともと3部構成になる予定だったが、映画版では3話目がカットされた。テレビでは第3話も放映されたという)。その第1話で描かれるのは、ワルシャワ蜂起に参加したポーランド人男性のエピソードだ。主人公は、危険が迫ると見るや、ためらいもなく演習から逃げ出すような男で、英雄からはほど遠い人物である。その男が、妻の愛人のハンガリー人を通して、反ナチのハンガリー勢力と国民軍(?)のあいだの伝令役を図らずも務め、やがて本当に英雄になるという皮肉な物語が描かれるのだが、ムンクはこの臆病者で日和見主義者の主人公を決して批判的に描いているわけではない。むしろ、この失敗に終わった蜂起をポーランド人が描く際のお決まりである悲劇的英雄主義のほうにこそ、批判の矛先は向けられている。この映画の脚本を書いたのは、イエジー・ステファン・スタヴィンスキー。同じくワルシャワ蜂起を描いたワイダの『地下水道』の脚本家だ。同じ歴史的出来事を、同じ脚本家が描いた映画でありながら、『エロイカ』のアプローチは『地下水道』のそれとは正反対といっていい。
周りで銃撃戦が起きていることにも気づかず、主人公が酔っぱらったように戦場をさまよう1話とは対照的に、第2話は閉鎖的な捕虜収容所内で展開する。ここでもテーマとなっているのは英雄主義だ。その収容所では、たったひとりだけ脱走に成功した人間がいて、それがいわば伝説になっている。だが、実は、彼は脱走などしておらず、収容所の屋根裏に隠れ住んでいたのだ。そのことを知っている数人の捕虜たちは、その事実をひた隠しにする。英雄の伝説が捕虜たちの希望になっているからだ。しかし、その一方で、その英雄主義が彼らの行動力を麻痺させていることをも、映画は描き出してゆく。 悲劇的英雄主義をロマンティックに描くワイダ作品とは、実に対照的である。ポーランド派の多様性を理解するためにも、『エロイカ』は『地下水道』と並べて見るべき作品だ。
『エロイカ』の次に撮られた長編『やぶにらみの幸福』は、いわば『エロイカ』の第1話の延長上にあるといえる。 「Bad Luck」という英語タイトルを持つこの作品の主人公は、自分が生きたポーランドの戦前から戦後にかけての激動の時代を回想しつつ、自分は「歴史の永遠の玩具」だったと嘆く。彼はなぜかいつも、間の悪いときに間の悪い場所に居合わしてしまうのだ。顔立ちのせいでファシストからはユダヤ人と間違われる一方で、警官にはファシスト扱いされ(2つのデモ隊にはさまれた彼は、どうしていいかわからず、ファシストのスローガンと反ファシストのスローガンをかわるがわる叫ぶ)、戦争が始まると、わけも分からないうちに次々と、ナチの協力者、闇商人、レジスタンスの伝令役などを演じていくはめになる。戦争が終わると、主人公はまずは偽弁護士となって金を稼ぎ、やがて、スターリンの社会主義を熱狂的に支持する役人として出世してゆく。
ゴンヴロヴィッチが書き直したヴォルテールの『カンディード』、あるいはポーランド版『フォレスト・ガンプ』とでもいうべきこの映画のなかで、主人公は歴史の様々な局面を通り抜けてゆくのだが、『エロイカ』の主人公同様、彼も自分の周りで起こっていることがまるで理解できないでいる。彼は身に降りかかる不幸を、自分につきまとう悪運のせいだと嘆く。だが、彼の不運の半分は、彼の日和見主義のせいだといっていい。周りで起きていることにわけもわからず順応し、皆がしていることを理解もせずに真似する。しかし、その間にも状況が変わっていることに気づかず、手痛いしっぺ返しを食う。その繰り返しが、彼の人生なのだ。
だが、『エロイカ』同様、ここでもムンクは、主人公を必ずしも批判的に描いているわけではない。たしかに、愚かな日和見主義者ではある。しかし、彼の愚かしさと、日和見主義は、無垢の裏返しでもあるのだ。風見鶏が変わるわけではない。風が変わるだけなのだ。先を見て動くのが要領のいい人間だとするなら、彼は決して要領のいい人間ではない。ただ愚かなだけで、彼はその場その場を、ある意味、真剣に生きてはいる。良くも悪くも、結局、彼はそうして生き延びるのだ。
この映画は、主人公のフラッシュ・バックというかたちで物語られてゆく。最初、彼が今いる場所ははっきりとわからない。勤め先をクビにされかけて、上司を泣き落としにかかっているところのようにも見える。しかし、最後の最後になって、彼が今いるのは監獄であり、今まさに釈放されようとしているところだということが判明する。なにをやっても不運につきまとわれるが、監獄のなかでなにもしないでいるあいだだけは、不運から逃れられると考えた彼は、もう一度牢屋に戻してくれと頼むが、それはできないと断られるところで映画は終わっている。『エロイカ』第2話の監獄のテーマはここでも別のかたちで変奏され、それは未完の遺作となった『パサジェルカ』へとつながってゆくことになるだろう。
△上に戻る
Masaaki INOUE. All rights reserved.