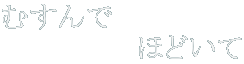
| 生まれつきの目の良さは、ずっと自分の武器だった。ぐるり見渡せる視界は広く、備わった動体視力はスラッガー並みに獲物をとらえる。コートの上でも、それ以外でも。 歴戦の武将いわく、情報を制したものが戦を制する。 目から入ってくる白も黒も大も小も全て分け隔てなく嗅ぎ分けて色分けして取り込んでは、牽制する道具にも身を守る盾にもしてきた。道も地図もない海の中を照らし、呼吸や進路を助ける、なくてはならない命綱。 ツンツン頭がトレードマークの地味で人のいい男は呆れながら言う。お前の場合は目がいいってんじゃなく、目ざといっていうんだよ。 はい全くその通り。実に的を射てる。 単に目がいいだけなら、深読みに長けたりしないだろうし、裏の意味まで求めたりはしないだろう。けど、この目は考えるより先にそれをやってのける。見ようとして見たものでなかろうが、視界をつかの間横切っただけだろうが構わず無差別に。我ながらややこしい性分とは思えども、その分降りかかる危険を回避して安全運転に専念できたのだから、感謝するほかない。 これは大した褒めるべきところのない自分に唯一与えられた才。生きていく上でプラスになりこそすれ、足を引っ張る要素になることはない。そう思っていた。いつだって自分の味方なのだと信じきっていた。その時までは。 「アンケート表持ってきた?」 「あ、あー……」 二度目の「あ」の発声はなかなかの悲壮感がにじみ出ていた。答えを聞くまでもない反応に落胆してか、千石を見下ろす瞳がわずか曇る。 「昨日までは覚えてたのになあ」 必死に鞄を漁ってみても、出てくるのは教科書ノートがたったの一冊ずつ。あとはケータイ、丸めたイヤホン、漫画に雑誌、コロンに汗拭きシートにブラシが二本とトランプなどなど、およそ学業に縁のないものばかり。机に収まりきらず、弾き出されて床に転げそうになったフリスクは間一髪、千石より小さい掌に救われた。感謝のしるしに目を細めて見上げれば、頷くと同じニュアンスで首を右に傾ける。散乱した机の隅に、小さな手がフリスクと少しの感嘆を置いた。 「荷物多いね」 「戦い抜くためにはいろいろ必要だから。ほら、言うでしょ? 男は一歩外を出ると七人の敵がいる」 我ながら適当なことを言っていると思った。中身のない台詞でも、人懐っこいジャムを添えれば大抵の女の子は笑ってくれる。目の前の女の子は別だけれど。 鞄から滑り落ちかけたタバスコを今度は反対の手がキャッチした。 「……タバスコ?」 「ヤンキー部員のあっくんに愛のサプライズ」 少しの間のあと、同情めいたため息とともに、千石の元に罰ゲームの申し子である赤い瓶は返還された。 「七人の敵では済まないかも知れない」 「敵多いように見える? この清純くんが」 「はい/いいえ/どちらともいえない」 「なにそのアンケート調査みたいな答え……」 うっすら彼女の口元が和んだ。不意打ちであらわれた、さざ波のような微笑みのかたち。すぐにそれは叱咤の色を持った。 「早く出してもらえると助かります」 「うっ、ごめん」 詰るよりも棘がなく、蒸し返すというには淡白な攻めは追い詰める意思がない。笑ってごまかすことを許されていると知りながら、あえて千石はその策をとらなかった。 「ほんとごめんねー」 眉を下げ、手を合わせて大げさなくらい詫びると、向こう側は少しだけ困ったようなうろたえた顔になる。それが見たかった。 「いいけど」 「いいの?」 「いやよくはない」 だよね、と喉の奥で笑い、イヤホンをカバンへ放り込もうとしたら制止された。 「絡まってるよ」 そう言ってコードを手にとった彼女は、神妙に結び目をひとつ解いてから千石に返した。千石はお礼がわりに最後まで机に取り残されていたフリスクを振ってみせた。 「食べる?」 目だけで仰ぎ見る。逡巡しながらも伸ばされた手のひらに、三粒、いや五粒サービスした。 「恋に効く味だって」 彼女が口に入れるのと同時に、ラベルの隅っこを走る宣伝文のひとつを読み上げると、面食らったのかメントールが効いたか、わずか目を見張ったのがわかる。 えへ、と憎めないと評判のスマイルを作ってから、フリスクを胸ポケットに滑り落とした。まっさらに片付けられた机には、いたずらに削られた傷しか見当たらない。その傷を撫でていた、机よりも更にまっさらな目が千石に向いた。 「書けたら出してね」 そっと落とされた声の、語尾はいくらか弱めに。そこには怒ってないよという彼女の意思表示が眠っている。千石は考える間もなく「うん」と吸い込まれるように頷いた。 真正面だった姿は背中になって離れていく。項を覆い隠し、背に沿って弾む黒い髪を名残惜しく見送った。 とっくに要項が埋められているアンケート用紙を、教科書の間から抜き取って、丁寧に折りたたんでからフリスクの奥にしまいこんだ。恋に効く味。ぴりりと舌に辛い。 女の子はみんな可愛い。生まれてきた瞬間から可愛い。特別美人じゃなくても、愛嬌さえあれば可愛い。更に言えば愛嬌がなくたってそこにいるだけで可愛い。 彼女は、はあまり笑わない。いや少し違う。わかりやすく笑顔をつくることができない。満面に気持ちをあらわすのが不得手で、いつも香る程度のものだから、単純に見逃しやすいだけの話だ。ほのかな変化は、真昼の空にある月のように目立たない。そのせいでときに冷めた印象を与えてしまうこともあるだろう。事実、千石もそう感じていた時期があった。 ただ、千石は人よりずっと視覚に優れているから。読み取ることに長けているから。目を凝らせばかすかに息づくものが見えた。かの内側は月の表面ほど冷たくはなくて、血も温度も感情も健気に温かく脈打っていると知るのに、いくらも時はかからなかった。目がいいから昼の月の輪郭もよく見える。目がいいせいで、昼の月が照らす矛先さえも。 少し時を遡る。そう、あれは三年に進級したばかりの、彼女の髪が背中にまだ届かない頃の話。 その日教師の急病で穴のあいた授業は、自習という名の自由に成り下がっていた。試験前ならいざ知らず、そうでないならバカ正直に勉学に勤しむ生徒はいない。野放しにされた教室は無邪気で騒がしくてまとまりがなくて、だから、誰も気づいていない。あれは一瞬の、本当に一瞬のことだったから、きっと他には誰も。 その時千石は誘われるまま、ゲームの輪に加わるところだった。背もたれの方を向いて座ったせいで、静かに本を読んでいるの姿がよく見えた。ゲーム機に電源を入れつつどのモンスターを倒すか仲間と話を合わせていると、落ちていた彼女の目線がふと持ち上がった。瞬間、その面差しが無防備なほどに崩れた。まぶしげに細められた遠い眼差しはどこか痛ましく潤む。 あ、と思った時にはすでに通り過ぎていて、彼女はまた本に顔を向けていた。束の間の出来事。幻のようで、けれども幻ではなかった。 例えばコートのベンチ、例えば野球部のフェンス、例えば図書室の窓辺。これまで幾度も目にしてきた、隠れるようにして誰か一人を見つめている女の子たちの、その顔と似て重なった。彼女たちが一番魅力的に輝く瞬間であり、千石が最も女性の美しさを実感する瞬間でもあった。これまで、目にするたび「女の子ってなんてかわいいんだろう!」とときめき、時にうっとりと幸福感さえ覚えていたのに、その時はどちらも胸を満たさなかった。代わりに、冷えた小石が投げ込まれたような心地がした。 気がついたらゲーム画面の真ん中でキャラクターが立ち尽くしていた。着ているのは絶望的なまでに火に弱い装備。退治するのは火を吹くモンスター。焼かれて焦げた。 彼女が投げた視線の先で背の高い後ろ姿が声を上げて笑っていた。 瞬きで払い落としても残像は去らなかった。中身を紐解いて見ようとも思わなかった。 小石を体のどこかに引っ掛けたまま、亜久津をからかい南を怒らせ自校他校問わず女子にちょっかいをかけていつも通りの時間を貪った。時折転がり響くかすかな音を聞かないようにして。少しでも先延ばしにしたかったのだろうと今ならわかる。 幸いにしてか不幸にしてというべきか、悪あがきは長くは持たなかった。 モンスターに丸焦げにされた日から間もなくして、とある流行が訪れた。 ちょっと貸して? と隣の机に手を伸ばしかけたところ、いつもは二つ返事で応じてくれる女子が、その日に限って何故か引きちぎるような勢いで千石からそれを取り上げた。 「いいけど、ケース外さないでよ! 絶対みないでよ!? 絶対だから! 誓える!?」 貸してはもらえた。ただし食いつかんばかりに鬼気迫る形相と脅し付きで。 消しゴムに相手の名前を書いて無事使い切ることができれば恋が叶う――――おまじないとしては、昔からよく聞く古典的な方法で、今更目新しくもない。けれど身近に成功例があれば真実味は増す。隣のクラスのある女子の片思いが成就したことをきっかけに、ここのところ女子の間で密かなブームを呼んでいた。 そんな折りに、ころりとの消しゴムが転がってきたのは、運命のいたずらと呼ぶほかない。彼女は気づいていなかった。机から落ちたことも、千石の方へそれがたどり着いたことも。 “見えてしまった?” いいや恐らく、意思を持って“見た”。 ずれていたケースの中身、四角く白いそれに刻まれていたのは、ボールペンが刻んだ男の名前。まるで拙い恋が宿ってるみたいに、ひらがなで頼りなく。 まぶしげな目が見ていた方角の、とある背中と合致した。いつか投げ込まれた小石が時間差でかこん、かこんかこんと訴えながら底に落ちていく。 腑に落ちる音は考えていたよりずっと冴えた残酷な響きだった。 人より目がいいくらいで、魔法が使えるわけでも、うなるような財力もない。宇宙の一粒にすぎない青い星、その青い星の片隅に住む矮小な生き物だから、できることは限られている。ちびちびとした飴を舐めて、綺麗なもの愛しいものを愛でる背景になって、楽しく生きていきたい。大きな夢はみない。そうだそうだと合いの手のようにポケットが震えている。携帯を取り出すと、先週声をかけた女の子からだった。「カラオケ行こ(はあと)」に「もちろん行く行く(はあと)」と返信して携帯を伏せる。すっと影が落ちた。その顔を見て、どこかギクリと後ろめたさを覚える自分が虚しい。 「千石くん、アンケート」 「あっごめん! ほんとにごめん!」 「まさかまた」 「かくなる上は」 「切腹とかいいから」 「ごーめーんなさーい……!」 「……締切まではあるけど、早くまとめたいってうるさくて」 「真面目だねえ」 「早く終わらせたいだけだとおもうよ」 垣間見える親しげな気配は誰に向けてのものか。手に数枚抱えたピンク色の用紙を持って「今週中には出してね」と言い残して去っていく。行先は、席に座ってアンケートを取りまとめている男子生徒だろう。放課後や休み時間、二人でせっせと作業にあたっているのを何度か見かけた。単なる面倒な仕事も、相手によっては心躍る時間になる。一分一秒が長ければいいと願う、甘酸っぱい味の。 アンケート係は公正を期すためにアミダくじで選ばれた。そのアミダは、千石が作った。この時点で公正さは既に失われていた。二人が選ばれることを前提に仕組まれた不正のアミダはその任を全うし、彼女と、そして彼女が見つめていた先の彼を選出した。目論見通り。 実を言えば、手を回したのはこれが初めてじゃない。密かに施した小細工の数は、ゆうに片手を超える。研修で同じ班になるように画策したり、買い出しをわざと二人に頼んだり、掃除を代わってもらったり。自然に、溶け込み、人知れず、足音を消して忍びのごとくに立ち回るのは、協調性としたたかさを持ち合わせた自分の得意分野だったから。 目ざとさが災いしてしまったあの日以来、昼の月から恋の香りはしない。熱を帯びた視線もこぼれださない。彼女が器用に隠しているのか、それとも自分が努めて目をそらしているせいなのか、千石にはもうわからないけれど。 彼と彼女の距離は、果たして今はどのくらいだろう。月と地球くらいは近づいただろうか。覗き込む気にはなれず、望遠鏡のレンズに蓋をした。 女の子は可愛い、みんな可愛い、中でも恋する女の子はとびきり可愛い。この胸が軋んで痛むほどに。とびきり可愛い女の子は、幸せであればもっとずっと可愛いに違いない。 今日一日、彼女の席は空だった。風邪をどこからかもらってしまったらしい。本来なら、今日こそ持ってきたよね? と少し怖い顔で詰め寄ってもらえるはずだったのに。代わりにもう一人の係に詰め寄られた。が、なんだかんだと理由をつけて胸ポケットの中身を守り通した。これぐらいはいいだろう。これくらい許してくれよ。お前から取り立てられたいわけじゃない。お前じゃないんだ。むしろなんていうかお前には、お前だけは。 理不尽と知りながらも殴りたくなるから、それ以上のコメントは差し控えたい。 根腐れしたような気持ちのまま机からノートとファイルを引き抜くと、端に何かがぶら下がってついてきた。絡まったイヤホンは所在なげに揺れている。 ああ、せっかく解いてくれたのに。 気落ちするとともに、結び目をとく時の彼女の真剣な眼差しを思い出して少し笑って、それから俯く。 最初に、絡まりを解いてあげたのは千石のほうだった。 更に時を遡る。襟元の校章は今よりひとつ若い色で、あの子の髪は背中にも肩にも届かず、今よりもっとずっと短かくて。 進路指導が行われた放課後だった。ようやっと解放された千石が、閑散とした教室にたどり着くと、同じく進路指導の順番を待つが机にべたりと伏せていた。しっかりカーテンが引かれ、ひとつの物音もしない。日頃の姿から、およそ突っ伏して寝るようなタイプには見えなかったので、具合でも悪いのかと揺るぎない女性への親切心から近づいた。 「どうしたの? 大丈夫?」 机に伏せられたまま、ゆっくりと彼女の目が千石を見た。体調の悪そうな顔色ではなかったが、あまり大丈夫にも見えなかった。どことなく途方にくれるような気配が眉目にあらわれていた。彼女は耳を塞いでいたイヤホンを抜いて、ぽつりと。 「イヤホン短いから……」 身を起こした机の脇には、音楽プレイヤーとこぶし大の黒いものがあった。 毛玉? それが絡まりすぎているコードの成れの果てだと一拍遅れて知った。ひどかった。線の大方が巻き込まれて、イヤホン部分だけがかろうじて生き残っている。年の離れた弟が好き放題にいじくり回して、気がついたらこうなっていたのだと。もうどこから手をつけていいかわからないと思いつめた顔が言った。 彼女が横たわっていたのは、眠いせいでも体調のせいでもなく、短くなってしまったイヤホンのせいだった。コードの長さを合わせるんじゃなくてコードの都合の方に自身を合わせていたのだった。 そんなことで。 たったそんなことで、生真面目に困って? せり上がってくるものをこらえて、でもちょっとだけ笑ってしまって、千石は、このかわいい女の子の為に何とかなんとかしてあげたくなった。もともと指先は器用な方だ。いくら嫌がらせみたいにでたらめな巻き方でも、もともと一本に繋がったものを元に戻すのはそう難しいことじゃない。まかせてと微笑んで、知恵の輪みたいにこんがらかったそれを、ひとつひとつ辛抱強くほどいた。 徐々に、着実に、悪い魔法がとけるように元の姿に戻っていくコードを見て、彼女は目を輝かせていた。感嘆の溜息を吐きつつ、すごいとも言った。何度も言った。ありがとうの発音は誠実だった。 昼の月がおぼろげでなく映るようになったのは、たぶんきっとその日から。 女の子はかわいい。かわいい女の子は恋をしている。かわいい人は幸せであってほしい。 |