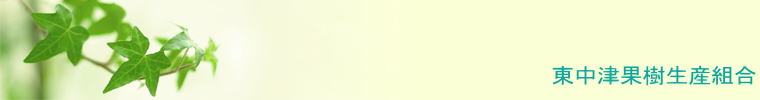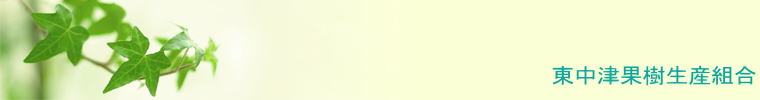|
|
 |
中津市梨(ナシ)産地の概要・歴史
中津市(旧中津市)は、大分県の西北端に位置し、面積56・06㎞2の約33%を山林原野が占め、山国川下流の平野部にまとまった農地が開けています。気候は瀬戸内海気候区に属し過去10年間の年平均気温は16℃、年間降水量は、1,459㎜です。
ナシ産地としての歴史は古く、その歴史は大正3年、岡山からの入植にまで遡ります。昭和10年には大貞園芸組合を設立、組合による市場出荷が始まりました。しかし戦中~戦後、食糧難、人手不足、食力増産の機運により「ソバ」・「ダイズ」等への転換が増加、ナシ園が減少しました。その後、再びナシ園の面積が増加、昭和30年代には「菊水」、昭和40年代中頃には「豊水」が導入されました。しかし、この頃になると産地が市街地に近いこともあり、近隣で宅地が増加し、それに伴い、庭木としてビャクシン類が新値され、赤星病が増加しました。
そこで昭和26年、中津市赤星病協議会を設立し、生産者と行政が一体となってビャクシン類の新植防止活動及びビャクシン類の共同防除体制を確立しました。また昭和27年より生産技術の向上を目的に農産物品評会を開催しており、今年で57回目となります。審査は「菊水」、「豊水」(有袋)、「豊水」(無袋)、「巨峰」の部があり、外観、玉揃い、糖度を基準に審査されています。
そして平成5年、果樹生産の振興を目的に中津市果樹生産協議会を設立し、栽培技術及び経営の向上を目的に講習会や剪定競技会等の活動を行っています。
|
|
|