|
「さんのいいところは食べっぷりが良さそうなところだよね」 「えっなに?た、食べ?」 「あと血行が良さそうなところ」 「血行?」 常に輝いている鳳長太郎のお目目が更に瞬いて星屑のステージみたいになっている時は、あまり関わるべきではないと承知していたはずなのに、あまりにも話の切り出しが唐突だったものだから、はまともに返事をしてしまった。 呆気にとられたをよそに、鳳はごく自然に隣の席を陣取った。 今日に限って窓際の隅っこなんかに座っていたせいで、そこを取られるともう逃げられない。退路は断たれた。 恐らく全てが無意識の上の行いであろう鳳は、よいしょと体をこちらへと向けた。 「相手の長所を見つけていくと良い人間関係を築けるっていうのを実践中なんだ」 世界が幸せになる100の方法。彼の手には自己啓発系と見られる本が握られていた。氷帝の図書室が誇る膨大な蔵書の中から何故わざわざそれを選んでしまったのか。ガンジーにでもなる気か。 「そんなことしなくても鳳君は良い人間関係築けてるんじゃないかなー」 だから必要ないだろうと続けるつもりだったのだが、鳳は照れ臭そうな顔をして「そうかな、だったら嬉しいな」とみるみるテンションを上げていった。しまった下手を打った、むしろ加速させたと後悔しても時すでに遅し。 鳳は身を前に乗り出して距離を詰めた。 「互いに尊敬することって人付き合いの基本だと思わない?」 「う、うん思うよ」 「短所より長所の方が見つける方が有意義だし自分も勉強になるよね」 「へ、へい」 元の清らかな資質に世界を幸せにしようと企む本の魔力が加わって、今日の彼はすごいことになっている。彼に限らず、自分も読んだり見たりしたものの影響をすぐに受ける口なので言動に異変が生じることを軽々しく責められないが、いささか今回のスーパー鳳くんは厄介な気がするので早めにボッシュートされて欲しいと思った。 それでね、と鳳は無垢な天使の翼を広げた(ように見えた) 「さんもさ」 「え」 さんも何だ。さんに何を求めているんだ。 「うちの部のいいところ探しを」 「あっごめん携帯が」 「逆じゃない?」 咄嗟に手を突っ込んだポケットには何も入っておらず、逆側の鳳が指をさしているポケットからこれでもかとストラップがはみ出しているのが見えた。 せっかく作った口実が秒殺され、はすごすごとポケットから手を抜いた。 「いいの?電話」 「勘違いだったみたいなんでいいっす……」 そう?と邪気なく微笑んで、圧力の変わらないただひとつの鳳長太郎は、それでさっきの続きだけどと何事もなかったように仕切り直した。 「うちの部のいいところ探しを」 一語一句変わらずリピートされ、さすがに聞こえなかったでは済まない。 しかし相槌をうつのもはばかられ、ただオウムのように復唱した。 「いいところ探し……」 「うん」 「うちの部の……」 「そう」 「なんでテニス部……?」 「部内での親交を深める為?かな?」 腕を組んだまま、鳳は可愛らしく小首をかしげて見せた。首を傾げたいのはこちらの方だ。 「いやそれなら」 部員同士でやりなよ、と至極まっとうな切り返しをしたところ、さんほとんど部員みたいなものでしょと思いもよらぬ鋭いカウンターを食らわしてきた。 正式に籍は置いていない。だが自然と、放課後この部室へ足を運んでしまう体になってしまったのは事実。 返事に詰まり、がプリッツを小刻みに前歯で噛み砕く作業に従事していると、鳳がその大きな肩を力なく落とした。 「それとも、さんは俺たちのこと仲間だと思ってないのかな……」 出た。鳳長太郎が伝家の宝刀を抜いた。 拒絶した側がなぜか悪人の称号を得る必殺善玉菌アタックだ。 これをあしらうのは容易いものではなく、よほどの神経の太さではなければかわすことはおろか、退けることもままならない。 は咀嚼したプリッツをごくりと飲み込んだ。 「や、やろうかな今後の為にも…」 暗雲が晴れるとでも言おうか。 途端、太陽が裸足で逃げ出すような笑顔を浮かべた鳳は、紙とペンをへ差し出した。 別に彼らに長所がないだとか探しようがないだとか、そんな根性の曲がったことを思っているわけではない。人にはそれぞれ美点が備わっているものだ。ただ、改めて考えるとなるとこれが意外と難しく、その人ならではの値打ちを書きだそうとしてもうまく当てはまる言葉が見つからない。要するに、圧倒的に語彙が足らなかった。人を称えるにも才覚がいる。 さっき鳳はのことを食べっぷりが良さそう、血色が良さそう、と評した。いま思えばもっと言いようがないのかという気もするが、所詮自分もその程度しか引っ張り出せないだろう。 良いところ良いところ良いところ は考えた。それはそれは根気よく考えた。 あんまりにもうんうんと必死で頭を捻っていたものだから、部員が揃ってそれを覗き込んでいることにもまるで気付かなかった。 「どれちょっと見せろ」 「あっ……!?」 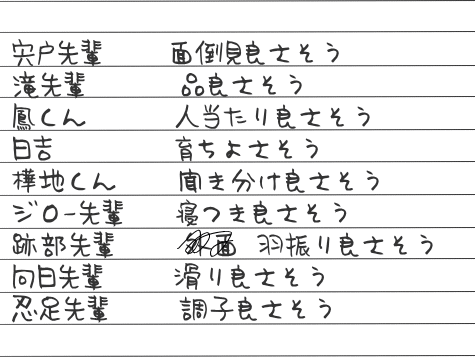 一瞬の静寂の後、怒声混じりの喚声がの耳をつんざいた。 オイィ――――――!!! 「おま…っこれどういうことだ!!」 「俺らの扱いだけおかしくね!!?」 「前半に比べて質落とし過ぎやろ!」 明らかに跡部を境に失速している誉めワードの紙きれを叩きつけ、後半に名を記された三人――― 跡部と向日と忍足は語気を荒げてに詰め寄った。 他の部員というと、表情に余裕を滲ませつつかしましく喚く連中を遠巻きに眺めているだけである。 それが余計に三人の神経を逆なでする。いっそみんな仲良く同等にこきおろされたなら、全員でつるし上げてやれば済むことだが、わかりやすく差をつけられてしまっては男として憤懣やるかたない。特に跡部あたりは台風が直撃した程度には荒れる。 「俺の長所は金しかねえみたいなことかオイ」 こめかみにぐりぐりとげんこつを当てられたは脳を稼働させすぎたことにぐったりしながらも、ノーノーと弱々しく言い訳めいたことを口走っていた。 違うんです決してそういうわけではなくってですねえーとボキャブラリーに乏しかったって言うかハイええごめんなさい痛い。 「先輩を賞賛する良い言葉が浮かばなかっただけであります」 「この消してある書きかけのやつなんだ」 「ご、誤字です」 「そとづら……」 「そんな日本語は知りません」 「どうせろくにその空洞の頭を使わず適当に書いたんだろうが」 「むしろ跡部先輩の項にいっちばん時間費やしたんですが……」 途端に跡部は眉を上げ、一瞬にして凶相を引っ込めた。 “いっちばん時間を費やした”という部分に機嫌を良くしたのは間違いないが、同時にお前の取り得がなかなか見つからなかった、という意味でもあることに、幸いにも気付くことはなかった。 「そんなに考えたのか」 「すっごい考えましたよ跡部先輩のこと!」 ふふんと誰に対してかわからない勝ち誇った笑みが浮かんだ。げんこつは平らな手のひらに変わり、二度ほどぽんぽんとの頭を叩くよう撫でた跡部は「お前らも早く準備しろよ」とさっさと言い残して消えた。その場に居たを除くすべての人間が、「偉大なるアホ」という同じ感想を抱きながら悠然と去る姿を見送ってしまった。 しかし跡部ほど目が眩んでいない残り二名が同じく引き潮のように潔く去るわけもない。 「俺らは騙されねーからな」 「騙したってなにを……」 「俺の“滑りが良さそう”って何だよ!?なんの滑りだよ」 「て、手櫛の……」 「手櫛!!!?」 「俺は?俺のあの調子良さそうってなんなん!?なにひとつ気持ち伝わらんアレなに!?」 「すいません、最後だったんでいわゆる弾切れで……言葉のノリです……」 「ええー……?ノッてへん、ノリって言う割に全然ノってへんよ?やっつけ仕事にもほどあるやん?聞いとる?」 「おいあんだろ他に、髪のツヤ以外に俺の輝かしい部分知ってるだろ!おい!手櫛はねーだろ!くそ!おい!!」 「私なりに精一杯頑張った結果です」 「あれが精一杯だったら普段俺らどう見えてんだよ!カマキリとかか!?」 「今まで結構仲良うやっとったやん……?あれ?もしかして知り合い以下なん?喋る丸眼鏡程度の認識なん?ちゃうよな?」 両者は縋るようにして肩を掴んで揺すったが、一日分の知性を使いきったは虚ろな目でされるがままになっていた。 「あーだめです店じまいです……いくら振られても今日はもう何も出てきませんよ……」 無我の境地よろしく無抵抗を貫くも、いいから書き直せよ!とプライドを賭けた氷帝D2に、日が傾くまでひたすらシェイクされ続けたは、不安定な視界を味わいながら人付き合いって難しいなあとしみじみ感じたのだった。 「そうだこれ、せっかくさんが書いてくれたんだから部室に貼っておきましょう」 「いいねー」 「よくね――――!!!」 |