 原図は藩政期に「鉄師頭取(てっしとうどり)」「下郡上座役人(したごおりじょうざやくにん)」といった、たたら製鉄師の役職を勤めてきた、出雲の絲原家の、絲原記念館
所蔵。この画像は「むらのかじや」さんにいただきました。ありがとうございます。
原図は藩政期に「鉄師頭取(てっしとうどり)」「下郡上座役人(したごおりじょうざやくにん)」といった、たたら製鉄師の役職を勤めてきた、出雲の絲原家の、絲原記念館
所蔵。この画像は「むらのかじや」さんにいただきました。ありがとうございます。いちばん左の男性が引っ張っているのが「箱鞴」のハンドル。鞴の横で炎が上がっているところが「火床」。
鞴を操作する人物との対比で、鞴のサイズが想像できる。
「はこふいご」と読む。吹差鞴(ふきさしふいご)、などとも呼ばれる。鍛冶屋にとっては神聖な、大切な道具の一つだ。
 原図は藩政期に「鉄師頭取(てっしとうどり)」「下郡上座役人(したごおりじょうざやくにん)」といった、たたら製鉄師の役職を勤めてきた、出雲の絲原家の、絲原記念館
所蔵。この画像は「むらのかじや」さんにいただきました。ありがとうございます。
原図は藩政期に「鉄師頭取(てっしとうどり)」「下郡上座役人(したごおりじょうざやくにん)」といった、たたら製鉄師の役職を勤めてきた、出雲の絲原家の、絲原記念館
所蔵。この画像は「むらのかじや」さんにいただきました。ありがとうございます。
いちばん左の男性が引っ張っているのが「箱鞴」のハンドル。鞴の横で炎が上がっているところが「火床」。
鞴を操作する人物との対比で、鞴のサイズが想像できる。
わりと最近まで歌い継がれていた小学校唱歌に、「村の鍛冶屋」というのがあった。もはや時代にそぐわないとして、当時の文部省により唱歌から削除されてしまった歌だ。
「村の鍛冶屋」
しばしも休まず鎚打つ響き
飛び散る火花よ走る湯玉
ふいごの風さえ息をも継がず
仕事に精出す村の鍛冶屋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この歌がこどもの親しむべき唱歌のリストから外されたのは、まさに、生産効率を追求し、零細の枝葉を切り捨ててきた高度成長時代の幻が、今もなお力を失っていなかったことを象徴しているといえる。
時代はポスト・バブルの長い長い不景気が今も続いている。日本経済高度成長黄金期に培われた地盤は傾き、もはや高度成長はありえないように思われるが、経済をその成長の度合いで評価せんとする、その土壌はいまだ健在のようだ。
しかし私には、生き物がそうであるように、経済もまた、成長には限界があるように思えるのだ。
私は経済の専門家でもなんでもない、ただのヒトなのだが、日本の経済は、成長期を過ぎて、オトナになる、すなわち安定すべき時期にきているのだと思う。そして直感的に、高度成長の土壌には高度成長しか育たず、私を含め多くの人々の(政府や経済界のトップの人々はいざ知らず)求めるような「安定」は根付くことはないようにも思えるのだ。
簡単な物理で、置かれた物体の安定は、底面内に重心の垂線が入っていなければならない。したがって、底面が広いほど、一般に傾斜にも強い安定を持つ。真の安定は底面の広いバランスがとれていなければ成立しえない。
強固な地盤が傾き、その上にぎりぎりのバランスを保って成長してきた「日本の経済」が倒れてしまった以上、立てなおすには、天辺を切り落として相当に高さを詰めるか、底部を相当に広く補強しなければ、再び底面に重心を入れて立ち上げることは困難だろう。
いま行なわれているリストラなどと呼ばれる作業は、その多くが、天辺を切り落とすのではなく、付け根を切り詰める作業に他ならない。付け根側を切り詰めて、わずかに残った天辺の部分だけで再生をはかろうというのだから、そもそも無理がある。そのうえ、切り捨てた付け根の部分は、雨ざらしに放置されて、腐るのを待つばかりという状態だ。
「村の鍛冶屋」は、現代から見ればお話にならないような小さな市場で、それでも需給のバランスがきっちりとれて、細々ながら手仕事が職業として成立した時代の歌だ。
今後必要なのは、その時代のような、とまでは言わないまでも、少数の人間がコントロールする、システマティックに巨大化した中央集権型ブラックボックス社会ではなく、底辺の広い、仕組みのわかりやすい、小さな社会の集合体としての社会の構築ではないだろうか。
鞴の話するのに、んなことまで考えるのもどうかと思うけどね。
ともかく、唱歌の歌詞にある、「ふいごの風さえ息をも継がず」のふいごで、漢字では「鞴」、または「吹子」と書く。
鞴とは、鍛冶屋が鉄をやわらかくして加工するための火の温度を挙げる目的で、火床(ほど)と呼ばれる炉に風、つまり強制的に空気を送り込む、空気ポンプだ。
炭のような固形燃料は、燃えていても放っておくだけでは鉄をやわらかくするほどには温度が上がらない。そこで、多量の空気、すなわち酸素を送り込んでやるのだ。すると火床の炭は轟々と吼えながら透き通ったピンクの炎を噴き出して燃え狂い、温度はただ燃えている時よりも数百度も上がり、鉄をオレンジ色に輝くやわらかい物質へと変えてくれる。これがなければ、鍛冶屋は仕事にならない、まさに飯のタネなのだ。
したがって、鍛冶屋の家では鞴は神聖なものとされ、鞴の由来についての神話もいくつか伝えられており、毎年旧暦11月8日には鞴祭りを催して感謝を捧げてきたのだ。
鞴にもいろいろなタイプがあるが、ここで述べる箱鞴というのは、技術屋風に言えば、手動のダブルアクション・プランジャタイプ・エアポンプだ。
注射器のように、ピストンを動かして流体を送るポンプをプランジャポンプという。
注射器はピストンを押すと中身を吐き出し、ピストンを引くと吸い込む。つまり注射器はピストンの特定方向の動きに対応してのみ出力されるポンプなワケで、このようなポンプをシングルアクションポンプという。
それに対して、ピストンの作動方向にかかわらず出力が得られるポンプを、ダブルアクションポンプという。
箱鞴とは、すなわち、手動でピストンを往復させて動かし、ピストンが押されるときも引かれるときも、往復とも空気を吐き出すことができる空気ポンプだ。この仕掛けは、チェックバルブとマニフォルドの組み合わせによる。
箱鞴のシリンダとなる鞴本体の内部には、ピストンで仕切られて部屋が2つある。どちらの部屋にも簡単な弁が2つずつ付いていて、ひとつはシリンダに空気を吸い込む時に開いて吐き出す時は閉じている吸入弁、もうひとつは逆に空気を吐き出す時に開いて吸い込む時は閉じている吐出弁だ。
このように、流体を一方向にしか流さない、逆流を止める弁を、チェックバルブとか、逆止弁と呼んでいる。
そして、吸い込み側の吸入弁は大気に開放し、吐き出し側の吐出弁は出口同士を一つの管にさらに集めてまとめて、そこに出口を設けている。このような集合管をマニフォルドと呼ぶ。
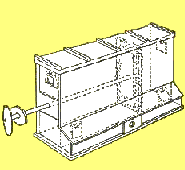
↑箱鞴(吹差吹子)の透視図
この画像は「むらのかじや」さんにいただきました。
ありがとうございます!
箱鞴のピストンを押すと、ピストンの前面側の部屋はせばまり、中の空気が吐出弁から出てゆく。吐き出された空気はマニフォルドに入り、吐出口から外に出る。そのとき、同時にピストンの後面の部屋はひろがり、吸入弁から外の空気を吸い込んでいるのだ。
ピストンを押し切ってから引くと、ピストンの前後で作動が逆になる。ピストンの後面側の部屋から空気がマニフォルドに吐き出され、マニフォルドから空気が外に出る。そのときピストン前面側の部屋は空気を外から吸い込んでいる。
ピストンの往復とも、ポンプ自体の空気の出口はマニフォルドの吐出口で共通であるため、ポンプからはピストンが動いてさえいれば必ず空気が吐き出されるのだ。シンプルで、巧妙なシステムだ。
私は2000年の夏、民俗学の資料などをもとに、現代版箱鞴を自作した。
現代版、というのは、要するに本来の材料が手に入らなかったり、あるいは現代の材料を利用してよりよく機能する可能性があったり、という部分に、本来の材料ではなく、今身の回りで手に入る材料を使用してみたのだ。
たとえば、ピストンのシールは本来狸の毛皮が使われていたが、起毛アクリルにした、とか(だいたい狸の毛皮なんてどこに売ってるのやら)、側板は杉の薄板でなくベニヤの化粧版を裏返しに使ってピストンのすべりをよくした、とか、弁は和紙でなく1mmのバルサ板を布のヒンジで吊って使った、とかだ。
私の箱鞴のサイズは、古い表現では尺五寸、すなわち長さ約45センチの、おもちゃのような小さなものだ。鍛冶屋の細工場の据付鞴は4尺(約1.2メートル)が普通だったというから、いかに小さいかがわかる。
とはいえ、非現実的なミニチュアではなく、山に入って木を切る木挽きの現場で工具を直すのに使っていた鞴の外観図や写真(それも作業中の)を参考にほぼ同寸法で作ったもので、まあ、出職用のポータブル箱鞴の復刻版というところか。その資料では、昭和も40年代までは、そんな鞴を実用にしていた人々がいたのである。今はどうなのだろう。
この鞴、使ってみると、なかなか具合が良かった。楢炭が轟々と熾るし、微妙な調整も自由自在にできる。
それまではヘアドライヤーを送風機に使っていたので、地面が濡れていると危険だし、鉄を打っているうちに炭が燃え尽きてしまわないようにいちいちスイッチをつけたり消したり、風力はせいぜい2段階にしか変えられないので火力の微調整はドライヤーを火床から離したり近付けたり、ドライヤーが振動でいつの間にか向きが変わってしまったり、と、面倒で使いにくかったのだ。
また、私のアイディアの化粧板やバルサ材の弁は動きが軽くて気密性も高く、大成功だった。
そして、鞴がこれほど操作に体力を使うものだということもはじめて理解した。
箱鞴の天板は、内部の潤滑や修理などのメンテナンスのために取り外せる蓋になっていて、資料写真などを見ると、鞴の上には鉄の塊や大きな石などの重石が載っている。これは、鞴の操作中は鞴内部の気圧で蓋が飛ばないようにしているのだと私は理解していた。
ところが実際に箱鞴を使ってみると、蓋が飛ばないだけの重量では、まったく不足だったのだ。鞴がピストンの操作に伴って、操作抵抗に負けてずり動いてしまうのだ。私の作ったような小型の鞴でも、重石が8Kgの鉄アレイではやや不安で、10Kgのダンベル用ウェイトで安心、という感じだった。蓋が飛ばないだけなら、私の鞴では2Kgも乗っけてやれば多すぎるくらいなのだ。つまり、このくらいの鞴でも、操作には10Kg近い物体をずり動かすだけの力が必要なのだ。しかも、停まっている物体を動かし始める力であるから、相当なものであり、それが操作中延々と要求されるのだ。
現代の鍛冶屋は、小さな工場でもほとんどすべて、鞴が電動のファン式送風機に取って代わられている。4尺の鞴ともなると1日動かし続けるのはとてつもない重労働に違いなく、これは当然の進化といえるし、悪いことでもなんでもない。
しかし、私は趣味のもぐり鍛冶屋であるから、生産効率を追求する必要もないし、一日中仕事を続けることもない。たとえ効率の悪い道具であろうと、「村の鍛冶屋」の歌など口ずさみながら、古の鍛冶屋に思いをはせつつ、楽しく鉄を打っていればいいのだ。
「村の鍛冶屋」に描かれているような古いスタイルの手仕事の伝承というのは、社会の変化が早くなるほど、難しくなっていくものに違いない。
私は技術屋だが、私の働く現場でも、たとえばもはやドリルを砥ぎなおして使う者などいないし、きちんと砥ぎなおせる者もいなくなってきている。理由は簡単で、いまやドリルを砥ぎなおす労力分の対価よりも安く、新品のドリルが買えるのだ。
名人芸や職人技は貴重だが、経済というシステムの中で費用対生産効率を追求される現場では、もはや必ずしも必要とされなくなっているのかもしれない。
これからは伝統的な手仕事を伝承していけるのは、超絶的な職人技を持って文部科学省とかから選ばれるような、生産効率度外視で仕事ができる身分の一部の人々と、私のように趣味で敢えて古いスタイルの手仕事にこだわる名もない人々だけなのかもしれない。
それが、進歩ということなのだ。